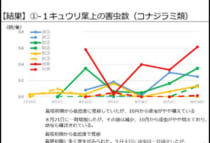令和7年度くまもと農業女性ネットワーク全体研修会の開催
球磨地域農業女性アドバイザーネットワークは、11月17日、全県組織のくまもと農業女性ネットワークと共同で、多良木町登録有形文化財「交流館石倉」において、県内の女性農業者を参集しての研修会を開催しました。
本研修会は、県内の女性農業者が明るく元気に働けるよう、各地の農業を学び、魅力ある経営と生活について楽しく語り合うことを目的としています。球磨地域での開催は平成24年以来で、県内全域から約100名の参加がありました。
プログラムでは、まず人吉市役所より令和2年7月豪雨による当日の被災状況から復旧・復興の状況についての講演が行われました。次いで球磨地域女性農業者有志による経営内容及び日々の営農風景の紹介がありました。
後半では、多良木町及び湯前町の住職コンビ「Seppo-CCQ」による漫才法話が行われ、現状を把握することの大切さや球磨地域で実際にあった食を通じた心温まるエピソードが紹介されるなど、笑いの中にも経営・生活を豊かにする上で、示唆に富む話を聞くことができました。最後に、球磨ネットワーク会員が厳選した球磨地域ならではの農産物及び加工品およそ40アイテムを持ち寄ったお楽しみ抽選会が行われました。
参加者には、研修を通じて球磨地域の農業の実情や特徴を知ってもらうとともに、終始、和やかな雰囲気での情報交換を行ってもらうことができました。
当課は、引き続きネットワークの活動支援を通して、女性農業者の経営参画や相互の交流の促進を図り、球磨地域農業の活性化につなげていきます。