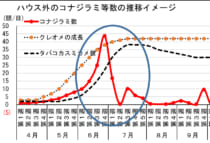宇城地域鳥インフルエンザ防疫研修会を開催
高病原性鳥インフルエンザが万一発生した場合には、まん延を防止し、地域経済への最小化を図るため、速やかに防疫措置までを完了することが重要となります。このため、4月22日に「宇城地域鳥インフルエンザ防疫研修会」を開催しました。
本研修は、宇城地域振興局及び果樹研究所の転入者を中心とした職員を対象に、毎年度当初に実施しています。特に本県では、過去に4月の発生事例もあり、できるだけ多くの職員に参加してもらえるよう、午前と午後の2部に分けて開催し、合計62名の参加がありました。
研修では、高病原性鳥インフルエンザの発生状況やマニュアルの改訂内容、管外および管内で発生した際の動員の流れや具体的な作業内容、体制等について説明を行い、動画を交えながら、自身の役割や防疫対応についての理解を深めてもらいました。
管内には県下最大クラスも養鶏場もあることから、農業普及・振興課では今後とも、発生の際に迅速・確実な対応ができるよう、特別防疫対策期間が始まる秋口までには、より詳しい研修や実地演習なども組み合わせながら、関係機関と連携して初動体制を構築していきます。