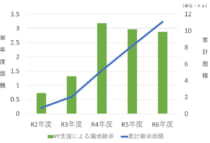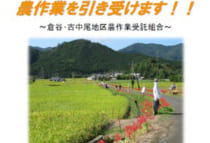~令和2年7月豪雨災害からの創造的復興を目指して~ 加工用ばれいしょを収穫しました
芦北地域では令和2年7月豪雨災害からの創造的復興を目指して、水田裏作として加工用ばれいしょの導入に取り組んでいます。
令和7年産は、JAあしきた及び管内営農組織と連携して、2カ所、計25aで栽培実証試験を行っています。5月28日に収穫を迎え、収穫機(ハーベスタ)を用いた機械化実証と併せて、この取組みを広く周知するため、地域の営農組織や芦北高等学校農学科の生徒らを招いた見学会を開催しました。
ばれいしょの収穫作業については、全体の作業時間に占める割合が最も大きく、収穫にかかる労力を削減すれば、栽培面積の拡大や雇用労働費の削減につなげることが可能です。今回使用したハーベスタは、運転手1名と選別作業員3~4名という少人数での作業が可能で、作業時間はハーベスタを使用しない場合の約1/2と、大幅な労力削減につなげることができました。
また、見学会では、営農組織からハーベスタの使用方法や処理能力に関する質問があったほか、高校生からは加工用品種の特徴について質問があるなど、加工用ばれいしょ栽培に興味を持つ様子が見受けられ、有意義な会となりました。
令和7年産の作柄としては、排水対策に課題が残り、目標としていた収量を達成することはできませんでした。
農業普及・振興課では、今後も引き続き、関係機関と連携して対策を検討・実証し、加工用ばれいしょの導入が農家の所得向上に結び付くよう取り組んでいきます。