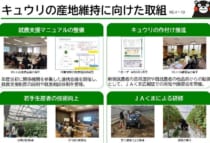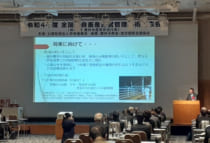第62回球磨酪農郡市乳牛共進会が開催
令和5年10月13日に第62回球磨酪農郡市乳牛共進会が球磨家畜市場にて開催されました。当日は、未経産牛の部に16頭、経産牛の部に20頭の出品があり、出品されたどの牛も酪農家の手入れに力が入っており、非常にレベルの高い共進会となりました。
オールジャパンブリーダーズサービス株式会社の釘田貴博氏による、厳選な審査の結果、各部においてグランドチャンピオンとリザーブチャンピオンが選出されました。
未経産牛の部でグランドチャンピオンに輝いた村田牧場の牛は、首から肩への移行がスムーズで、肋骨の間隔が広く中駆が充実していると評価されました。また、経産牛の部でグランドチャンピオンに入賞した椎葉牧場の牛は、体と乳器のバランスに優れ、前乳房の付着が強く、後乳房の付着点の高さと幅が優れていると評価されました。
農業普及・振興課では、今後も共進会の開催支援等を通して、乳牛の飼養技術の普及・向上を支援してまいります。