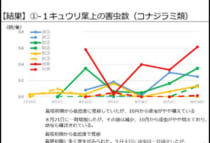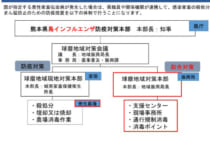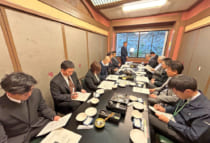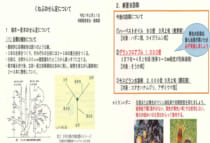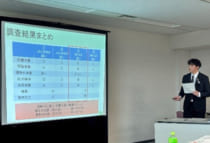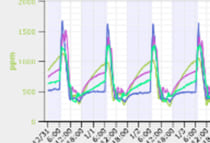球磨地域特定家畜伝染病に係る防疫演習の開催
球磨地域振興局では、10月20日に錦町の勤労者体育センターにおいて、球磨地域特定家畜伝染病に係る防疫演習を開催しました。
当地域では、毎年度主に鳥インフルエンザの発生を想定した、防疫演習を実施してきましたが、本年は新たに、豚熱の防疫措置に関する項目を加え、座学と実演の2部構成で開催し、管内市町村、関係団体等約80名が出席しました。
まず座学においては、城南家畜保健衛生所から特定家畜伝染病の発生状況を、当課からは発生時の初動対応にかかる後方支援を、森林保全課からは野生いのししにおける豚熱感染の対応を説明しました。
次に実演では、養豚場での豚熱発生を想定した、殺処分の流れを豚の模型を用いて説明し、鳥インフルエンザと豚熱での発生時の対応の違いについて、参加者に理解を深めてもらいました。
演習後のアンケートでは、「発生時の自分の役割を理解できた」、「牛などの口蹄疫が発生した場合の対応を聞きたい」などの意見があり、今後の防疫演習の内容に活かしていきたいと考えています。
特定家畜伝染病が発生した場合は、地域全体で防疫措置を実施する必要があります。
鳥インフルエンザでは、すでに北海道の養鶏場で感染が確認され、近隣の県では豚熱に感染した野生いのししの発見が続くなど、予断を許さない状況です。当課では、万が一の発生に備え、関係機関との連携を強化し、特定家畜伝染病の発生リスクの低減に取り組んでいきます。