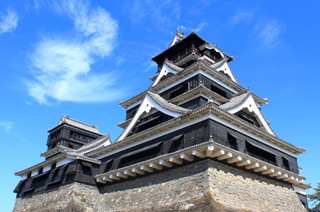令和7年産「太秋」生産始まりました!
「太秋」は大玉で糖度が高いことが魅力である柿の品種の一つであり、熊本市では柿の生産量(R5年産59t:令和5年産果樹振興実績より)のうち80%以上を「太秋」が占めています。特に植木町は、熊本市の「太秋」生産量の約70%を占めるなど、生産が盛んな地域となっています。
「太秋」の大玉果生産には着蕾確認後から開花前までの短い期間内の摘蕾作業が極めて重要です。この時期の管理が適切に行われない場合、高単価商材となる大玉生産に大きな影響を及ぼします。そこで、この時期の適期管理の重要性を周知するため、JAと協力し「太秋摘蕾講習会」を4月22日に開催しました。また、当課からは栽培管理指導に加えて、農作業安全対策についても啓発を行いました。高品質果実の生産だけでなく、生産者が安全に作業を行うよう併せて指導を行うことで、持続可能な農業の実現につながることを期待しています。講習会では、摘蕾管理だけでなく、病害虫防除の効果的な方法についても活発な質疑応答が行われ、これからの高品質果実生産に向けた有意義な講習会となりました。
令和7年産の「太秋」でも高品質で大玉果が生産できるよう、当課では引き続き生産者への技術的な支援を行っていきます。今後も、栽培管理の向上と安全対策の強化を進め、持続可能な果樹生産の実現を目指します。