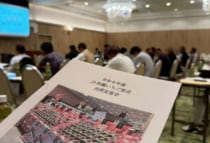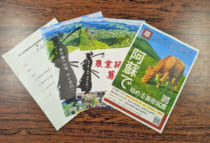農林部3課合同での現地研修会の開催
現在の農業情勢は、高齢化・担い手不足、耕作放棄地の増加といった課題に直面する一方、規模拡大と経営効率化を図るため基盤整備やスマート農業技術の導入が進められています。当局農林部では、地域が抱える課題について農林部3課全職員が情報を共有するため、今年度は3回(9テーマ)の現地研修会を開催します。
11月14日には2回目の研修会を実施し、当課からは、ICTを活用した放牧看視システム「うしみる」について、産山村下平川牧野にてシステムの概要及び阿蘇地域の放牧状況について説明しました。職員からは金額面や導入事例に対する活発な質疑がありました。
林務課からは産山村の林地内にて「人工林の管理・伐採状況」について、農地整備課からは大蘇ダムの現地にて「大蘇ダムの現状及び今後の見通し」についての説明がありました。
この研修会は、他課職員が滅多に足を運ぶことがない他分野の現地を視察でき、阿蘇地域の農林業が抱える現状、課題及び各課の取組みをより深く理解するための一助となっています。また、他課とつながりをつくることで、連携が必要な際、相談がしやすい環境づくりにも繋がっています。次回は、2月を予定しています。