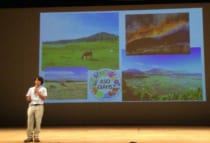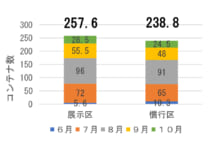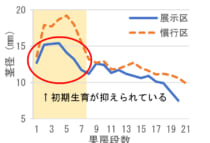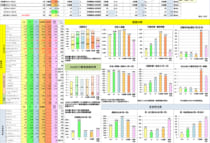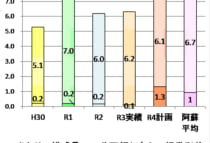「阿蘇地域世界農業遺産」認定10周年!
阿蘇地域の「草原の維持と持続的農業」が世界農業遺産に認定されて、今年で10周年を迎えました。このことを記念し、10月12日(木)に阿蘇の司ビラパークホテルにて、「阿蘇地域世界農業遺産認定10周年記念シンポジウム」を開催しました。
プログラム内のパネルディスカッションでは、生産、食、流通、報道、学術、行政それぞれの分野の専門家にパネリストとしてご登壇いただき、「阿蘇の持続的農業を未来につなぐために」をテーマに意見交換を行いました。
本式典には、県内外から約200名の方にご参加いただき、阿蘇の農業と草原を守るために私たちに何ができるか、一緒に考えるきっかけとなりました。
翌日13日(金)は、41名の参加者を対象に、北コースと南コースに分けたエクスカーションを実施しました。あか牛放牧や牧野散策といった草原の活用状況のほか、水源や資料館等、阿蘇の農業遺産を構成する資源を案内し、阿蘇に対する理解を深めていただいたところです。
今後も、当課では世界農業遺産の周知・PRを通して、阿蘇の農畜産物の認知度が全国的に広がるような取り組みを、関係団体と連携しながら進めて参ります。