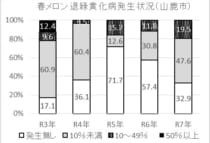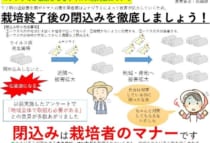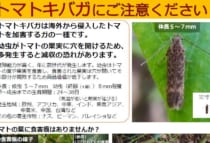鹿本地域家畜伝染病防疫演習の開催~防疫体制の役割と現場事務所の流れを確認~
11月7日、鳥インフルエンザなどの悪性家畜伝染病発生時に迅速かつ的確な防疫措置ができるよう備えるため、山鹿市環境センターで鹿本地域家畜伝染病防疫演習を開催しました。当日は建設業協会や関係団体等も含め、約60名の参加がありました。
演習は、座学と実地演習の2部構成で行いました。座学では、当課からは管内で発生した際の防疫体制(後方支援)について、関係機関の役割分担やその具体的な内容など、「鹿本で鳥インフルエンザが発生した際、それぞれの機関が何をしなければならないか」を周知しました。実地演習では、防疫作業の最前線基地となる現場事務所設置・運営の実演を行い、現場事務所の各係の役割や、他地域の防疫作業に動員された場合の現場事務所での動きについて実演を行いました。実際にテントや資材を設置し、配置や動線について確認を行うことで、発生時の動きを確認することができた一方、関係機関との更なる連携が必要という課題も浮かび上がりました。
今シーズンも、九州を含む複数の県で鳥インフルエンザが発生しており、いつどこで発生してもおかしくない状況です。今回の演習及び検証結果等を基に、発生に備え、迅速かつ的確な防疫対策が行えるよう関係機関と連携し、より一層の体制強化に取り組みます。