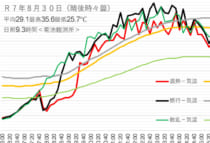小学生のいきなり団子づくりを食の名人がお手伝い
11月26日、大津町在住のふるさと食の名人2人を講師として、大津町立大津北小学校の5、6年生の10人が、大津町特産のからいもを使った「いきなり団子」作りを行いました。生徒たちは、食の名人から団子の生地の作り方や包み方などを教えてもらい、楽しみながら調理に取り組みました。調理後は、作ったいきなり団子を食べ、「おいしい」との声を上げていました。実施後のアンケートには、「かわの包み方が難しかった。」「いきなり団子の作り方を初めて知った。」などの感想と食の名人に対する感謝の言葉がありました。
今回の授業は、くまもとふるさと食の名人・小中高等学校等派遣事業(出前講座)を活用し実施されたもので、農業普及・振興課では、実施に向けた食の名人との日程調整や小学校との打ち合わせを行いました。
当課では、食の名人の活動に対する支援を通して、子供たちの食への関心が高まり、地域農業への理解が進むことを目指し今後も取り組んでまいります。