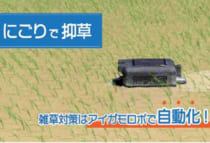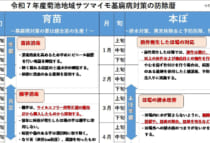県北広域本部・菊陽町合同家畜伝染病防疫演習を開催
今年も鳥インフルエンザが流行するシーズンに入りました。県北広域本部では毎年このシーズン到来に先立ち、菊池管内の市町と合同で悪性家畜伝染病の発生時に備えた演習を開催しています。今年度は10月16日に菊陽町民体育館にて菊陽町と合同で行いました。
演習は座学と実地演習の2部構成で行いました。座学では、城北家畜保健衛生所から悪性家畜伝染病の発生状況について、県北広域本部からは菊池管内発生時の後方支援について、そして菊陽町からは菊池管内発生時の町の役割について説明しました。
実地演習では、消毒ポイントや、農場内の防疫作業にあたる職員の拠点となる支援センターや現場事務所の運営について、実際の道具や資材を用いて説明しました。また、今回は鳥インフルエンザと豚熱の発生時の対応の違いや、鳥インフルエンザ発生時の焼却処分の対応を踏まえた内容も説明し理解していただきました。
今回の演習を通して、管内発生時に設営作業にあたる県や市町の職員とともに設営や作業手順の確認を行うことで、課題の洗い出しをすることができました。
今シーズンも既に鳥インフルエンザの発生が確認されており、いつどこで発生してもおかしくない状況です。今回の演習を踏まえ課題を改善し、迅速かつ的確な防疫作業が行えるよう関係機関と連携することで、より一層の体制強化に取り組みます。