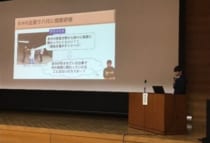菊池えごま生産組合の取組紹介 ~第4回立毛品評会と令和5年産えごまの収穫・販売~
菊陽町、大津町の生産者で構成される菊池えごま生産組合(代表:上村幸男組合長)では、えごまの栽培技術向上のため2020年から立毛品評会を開催しています。
本年は9月19日に第4回立毛品評会の審査を行い、えごまの生育やほ場の管理状況を採点しました。前年から施肥設計の改善等に取り組み、天候にも恵まれた結果、審査を行った10ほ場のうち8ほ場で、前年1位の得点を上回る素晴らしい結果となりました。特に、えごまの子実収量と関係する2次分枝数は全てのほ場で10点満点(令和4年平均:6.6点)であり、前年からの収量増が期待されます。
2023年産のえごまは10月末~11月初旬に子実の収穫を行い、乾燥、脱穀、搾油を経て「きくちのえごま油」の名称で販売されます。なお、同商品は菊陽町のふるさと納税の返礼品にも指定されているほか、令和4年産からグリーンコープでの販売が始まるなど、様々な経路で入手できるよう販路開拓が進められています。
えごま油に多く含まれる「α-リノレン酸」は健康効果が期待されており、メディア等で紹介される機会が増えています。また、えごまはイノシシ等の食害に遭遇しにくく、連作が可能なため、中山間地の経済作物としても有望です。農業普及・振興課では、関係機関と連携しながら当組合の活動を引き続き支援いたします。