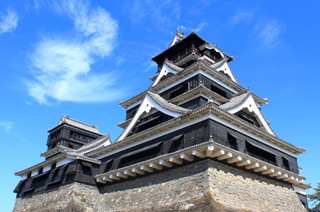いちごの出荷始まる ~生産者の所得向上を目指して~
JA熊本市白浜苺部会(部会員数18名)では、河内町白浜地区で約7haを作付けされています。
今年度も、昨年同様秋季の高温の影響で花芽分化が遅延し、例年と比べて10日程度遅れての定植となりました。部会からは、年内収量及び総収量の確保を心配する声が挙がったため、以下の取組を行いました。
まず、9月に頂果房の花芽分化確認後の定植を実施しました。次に、生産者からマルチ及び天井ビニールの展張日に関する質問があったことから、その判断の基礎資料とするために、10月に第一次腋果房検鏡を実施し、展張基準日を決定しました。
その結果、11月25日から出荷開始となり、年内収量を確保できる見込みとなりました。
12月上旬には、いちごの品質低下及び年明け後の株の成り疲れによる減収を防ぐために、生産者とその従業員を対象に摘花・栽培管理講習会を実施しました。そこでは、生産者のほ場で摘花方法を実演し、現場の生育状況に応じた摘花方法を指導しました。生産者・従業員からは、「どの花をどの程度摘花すると良いかわかった」等の声が挙がりました。
現在、生産者5名を対象に、環境モニタリング装置を設置しています。当課では、生産者がデータに基づいた栽培管理を実施し、収益向上に繋がるよう引き続き指導していきます。