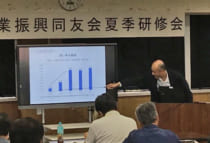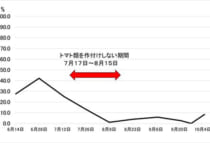耕蜂連携開始~持続可能な中山間農業へ向けて~
和水町平野地区では16年前から緑肥作物として水田裏作にレンゲを播種し地力増進に努めています。しかし、近年、種子代が高騰しているため、十分な播種量を購入できない状態でした。そこで、県内の養蜂家と連携し、播種量の半分となるレンゲ種子を養蜂家から提供してもらい、レンゲ開花後採蜜場として提供することで、耕種農家と養蜂家両者にメリットがある「耕蜂連携」の取組みを行うことになりました。地区水田全体での取組みであり約23haになります。10月上旬には稲刈りが行われ、耕起後の10月下旬、レンゲが播種されました。
また、今後高齢化が進んでも平野地区全体での取り組みが継続できるよう、播種作業の省力化を目的として20aのほ場にて水稲立毛ドローン播種試験を実施しました。播種は、稲刈り1週間前の9月29日、水稲立毛中にドローンによりレンゲ種子を播種しました。今後は、省力化にかかるデータ収集及び発芽・開花状況を確認し、来年度以降取組み可能な技術であるか検証していきます。
当課では、中山間地域における持続可能な農業経営の検討、また、地域営農組織等の取組み支援を継続していきます。