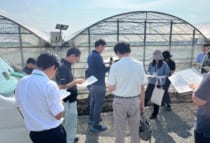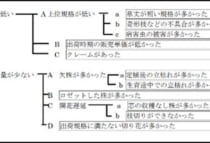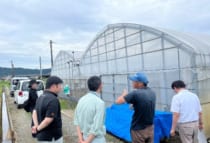宇城地域家畜伝染病防疫演習を開催~支援センターでの一連の流れを再確認~
宇城地域では、鳥インフルエンザ等の家畜伝染病発生時、迅速かつ的確な防疫措置ができるように備えるため、11月5日、宇城市不知火防災拠点センターにおいて、悪性家畜伝染病防疫演習を開催しました。
宇城地域では、防疫演習として毎年「座学+実地演習」を組み合わせており、今年は支援センターの設置・運営について、実際の会場を使用して演習を行いました。 当日は、市町や警察等関係機関を含め約50名の参加があり、座学では、家畜伝染病の発生状況や発生時の防疫対応の流れ、後方支援体制と業務内容の講義を行いました。
その後、隣の不知火体育館へ場所を移し、実際と同じレイアウトで各ゾーンに分け、受入れから送り出しまで運営側の業務の流れと応援者の動線等について確認を行いました。また、宇城保健所の指導の下、防疫服の着脱訓練も併せて実施しました。実際と同じ人と時間の流れを確認しながら訓練することで、運営スタッフとなる職員も、それぞれの役割について、より理解を深めることができました。
開催前日には今シーズン3例目となる新潟県での疑似患畜が確認されており、農業普及・振興課では、今後も万が一の発生に備え、迅速かつ的確な防疫対応ができるよう関係機関と連携して、より一層の体制強化に取り組んでいきます。